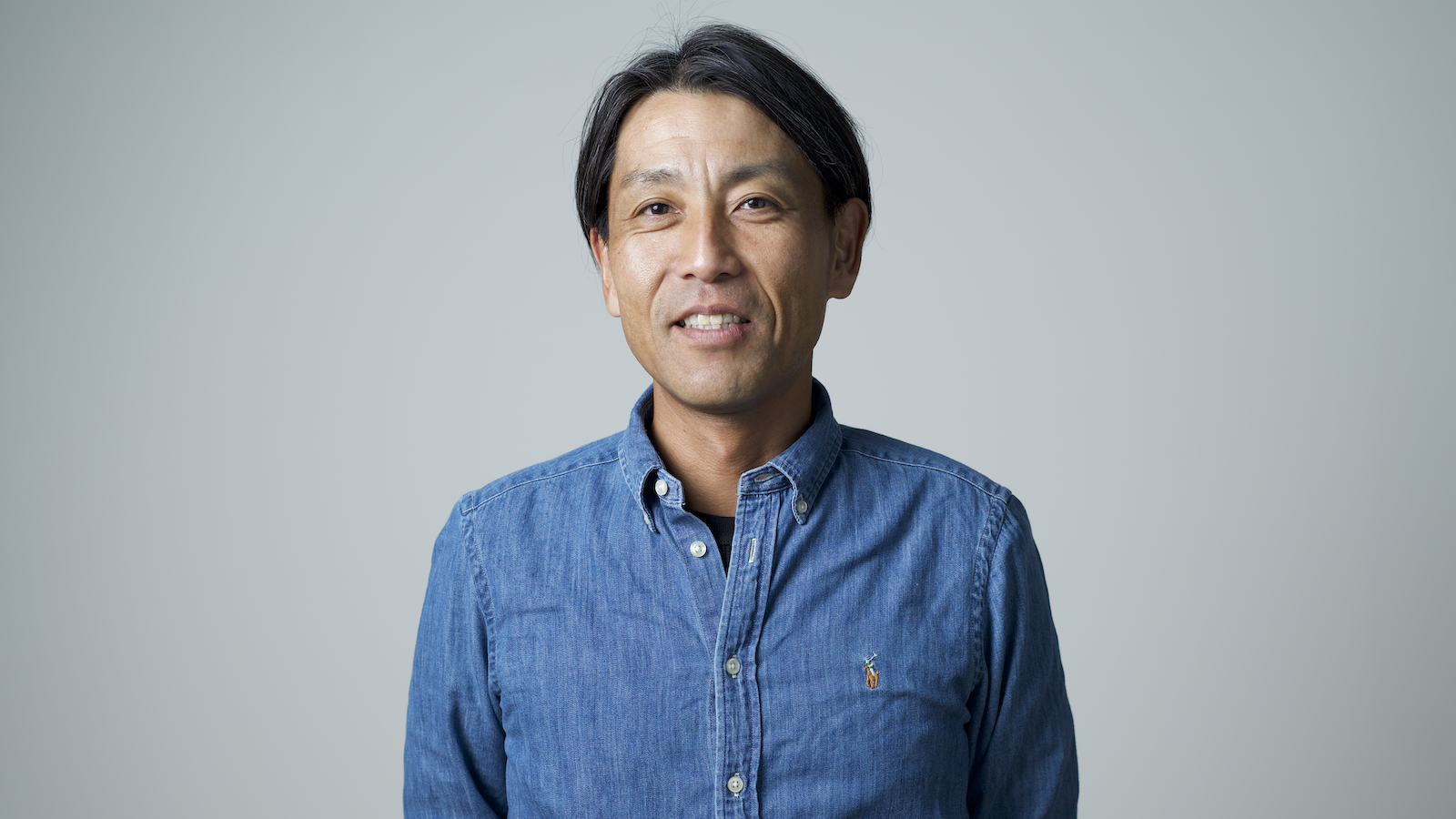この記事は、トレンドの原動力を探るマーケティングセミナー「よげんの書」で発表した「よげん」をトピックごとに解説した記事です。よげんの書のウェブサイトから無料セミナーのお申込みや、講演資料やアーカイブ動画をご覧いただけますので、ご関心ありましたらお申込みください。
近年、上場企業による中期経営計画(中計)の公表が増加し、2024年度は過去最多の696社が発表しました。これは株主からの要請が背景にありますが、経営層の視野は短中期に寄りがちであり、長期視点の欠如が成長を阻害している可能性があります。
短期志向の限界と長期志向の優位性
CFOへの調査では、経営の視野が「3年後」と「6年後」にそれぞれ約4割が集中しており、10年以上先を見据える企業は17%にとどまっています。短中期での成果を求められると、10年後の成長のための長期投資や人材育成が犠牲になりやすいという側面があります。
しかし、実際の業績を比較すると、長期視点の重要性が明らかになります。
1〜6年視点の企業: 直近の営業利益の伸び率は平均18%。
10年以上視点の企業: 営業利益の伸び率は平均52%。
10年以上の視点を持つ企業は、人材育成や長期的な投資の効果がしっかりと業績に現れる結果となっています。
中計発表の市場への影響は限定的
株主の要請で中計の発表が増えていますが、市場への影響は限定的です。中計発表後10営業日の株価は平均でわずか+0.2%の上昇にとどまり、効果は限定的で持続性に乏しいと評価されています。中央値で見ると-0.6%と、半数以上が発表当日を下回る結果となっており、中計が「高リスク低リターンの催し」になりがちであるという指摘もあります。
長期視点を持つ企業の事例
持続可能な成長を実現している企業は、長期的な視点を持っています。
オービック型(長期の土台): 営業利益が32年連続で過去最高を更新する見込みのオービックは、短期KPIよりも長期の安定成長を重視し、人材とクラウドへの投資を継続しています。
味の素型(ローリング運用): 味の素は2023年に従来の中計に縛られない運用に切り替えました。2030年のロードマップと共有価値を示しつつ、足元の戦略は機動的に変化(ローリング運用)させる体制を取ることで、中計病(硬直化)の回避を図っています。
企業は中計への依存を減らし、遠いビジョンと資本配分の進捗で市場と対話する長期視点の経営が、成長のヒントとなります。