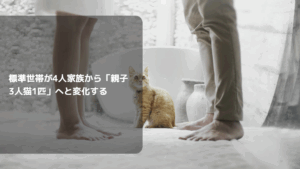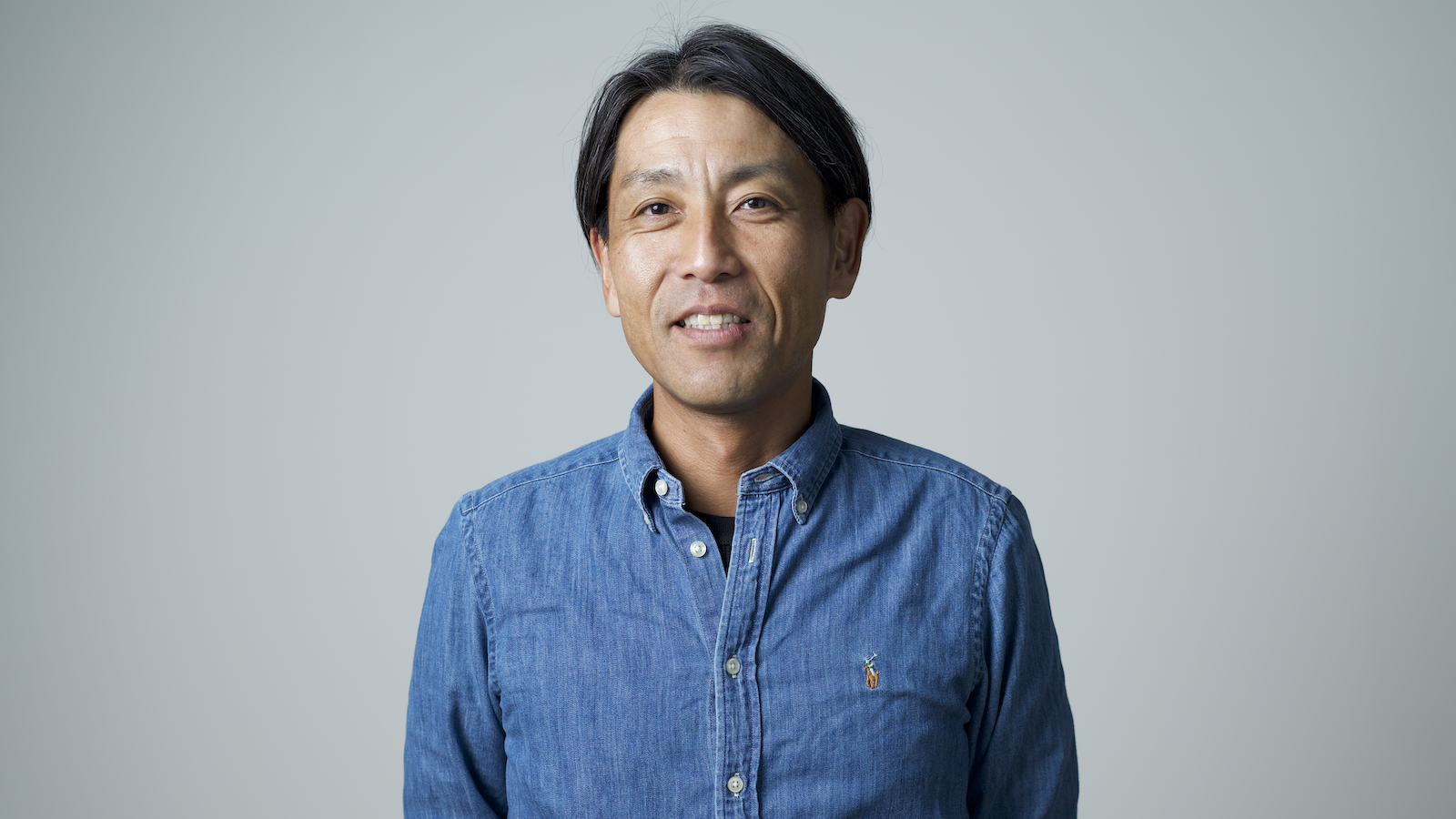この記事は、トレンドの原動力を探るマーケティングセミナー「よげんの書」で発表した「よげん」をトピックごとに解説した記事です。よげんの書のウェブサイトから無料セミナーのお申込みや、講演資料やアーカイブ動画をご覧いただけますので、ご関心ありましたらお申込みください。
日本の標準世帯の概念が変わりつつあります。少子化が進む一方で、犬や猫といったペットの存在感が増大しており、彼らが家族の主役を代替しつつあります。
出生数を超える新規ペット飼育数
2024年の日本の出生数は68.6万人で過去最小を更新しましたが、新しく飼われ始めた犬猫の数は80.3万匹と、出生数を約2割上回りました。 総数で見ても、15歳未満の子どもが約1,400万人なのに対し、犬猫の飼育数は約1,595万匹と上回っています。
ペット市場の拡大と多様化
医療やフードの進歩によりペットの長寿化が進み、小型犬は平均15歳近くまで生きるようになっています。これにより、子どもを中学生まで育てるのと近い感覚で、長期的な支出が発生します。 ペット市場は多様化しながら拡大し、2023年度には1兆8,629億円に達し、過去10年で1.3倍に成長しています。2027年頃には2兆円を超える勢いです。
市場の革新事例
絆を深めるサービス: 首輪のデバイスがペットの動きを計測し、AIがまるでペットと会話しているかのようなLINEメッセージを飼い主に送る「waneco talk」のような見守りサービスが登場し、絆と安心感を高めています。
高度な健康管理: 物言わぬペットの健康のため、人並み以上に支出が進み、腸内フローラ判定や乳酸菌サプリ、フレッシュ食などが広がっています。
代替ロボットの台頭: ペットを飼えない人向けに、体温が約38度ある「LOVOT」のようなペットロボットが、家庭だけでなく1,000の法人に導入されるなど、受け皿となっています。
経済的・社会的価値
小型犬の生涯費用は270万円を超えますが、子どもを15歳まで育てる費用(1,900万円)の約7分の1であり、経済的な面からも飼育が選択されやすくなっています。 ペットの飼育はウェルビーイングに良い影響を与え、金銭換算すると年収プラス1,300万円相当に匹敵し、結婚と同等の価値があるとされています。また、犬を飼う高齢者は認知症リスクが約4割減り、介護費用が半減するなど、社会的な効果も確認されています。
ペットは、家族の不安や孤独が強まる社会において、「裏切らない理想の家族」として見なされており、共に生き、共に眠りたいという需要から、ペットと一緒の墓を望む女性も3割を超えています。