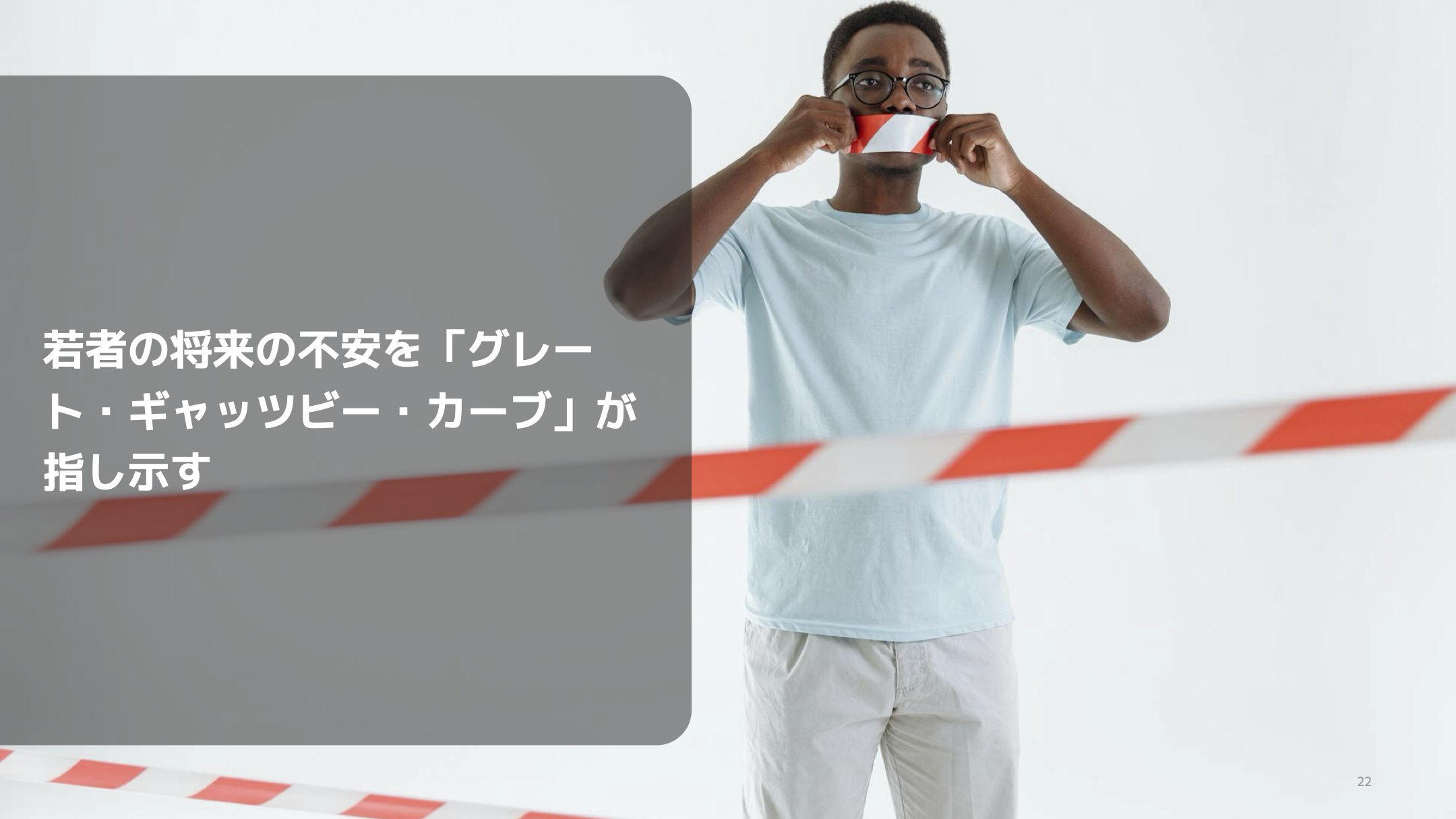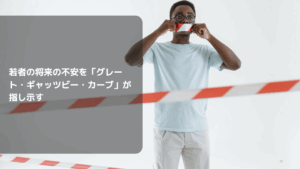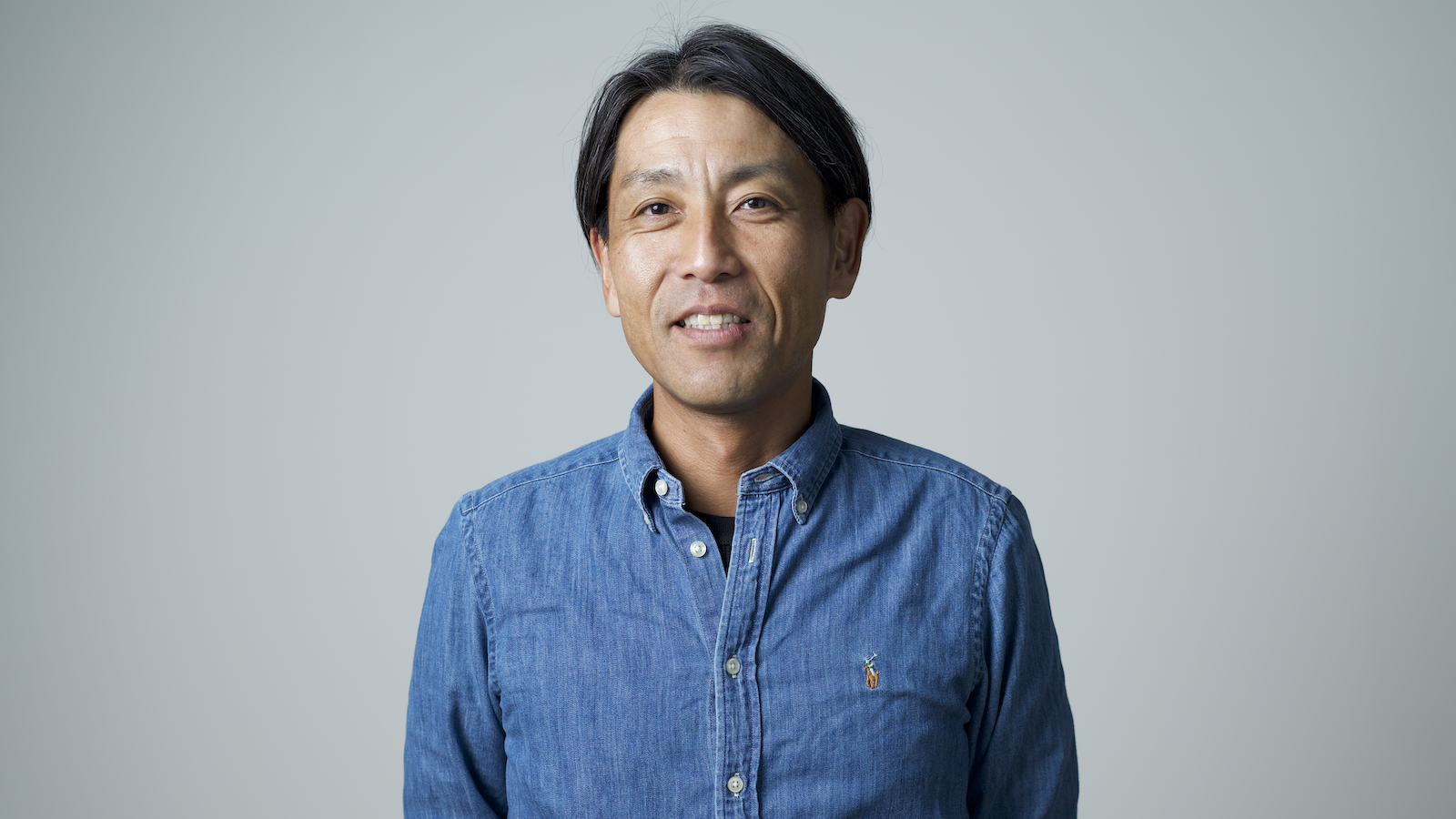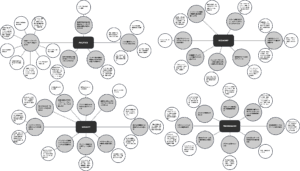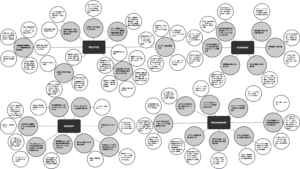この記事は、トレンドの原動力を探るマーケティングセミナー「よげんの書」で発表した「よげん」をトピックごとに解説した記事です。よげんの書のウェブサイトから無料セミナーのお申込みや、講演資料やアーカイブ動画をご覧いただけますので、ご関心ありましたらお申込みください。
若者の将来の不安を測る指標の一つとして、「グレート・ギャッツビー・カーブ」があります。この概念は、経済的不平等(格差)が高い国ほど、親の所得が子どもに引き継がれやすい(階層が固定化しやすい)という相関関係を示すものです。
これは、格差が大きい社会では「努力で階層を上る」ことが難しく、個人の将来が生まれ育った家庭に左右されやすいことを意味します。日本でいう「親ガチャ」という言葉が、この社会状況を体現しているとも言えます。
OECD主要25カ国のデータに基づくと、米国やメキシコは不平等が高く固定化しやすい右上、社会保障が広く強い北欧諸国(フィンランド、デンマークなど)は左下に位置づけられ、日本とフランスは中間に位置しています。米国では、かつて「誰にでも機会がある」とされたアメリカンドリームは、もはや神話に過ぎなくなっている可能性が指摘されています。
統計的にも、主要10カ国において、子どもが親の所得を超えられる確率は低下しており、特に日本、米国、フランスで顕著です。現在、子の2人に1人しか親の所得を超えられておらず、富裕層の資産の6割は相続や独占によるものです。
この格差固定化の問題を解決する鍵として、グレート・ギャッツビー・カーブは教育との相関が深いとし、教育の質を高め、機会の平等を確保することが重要であると示唆しています。