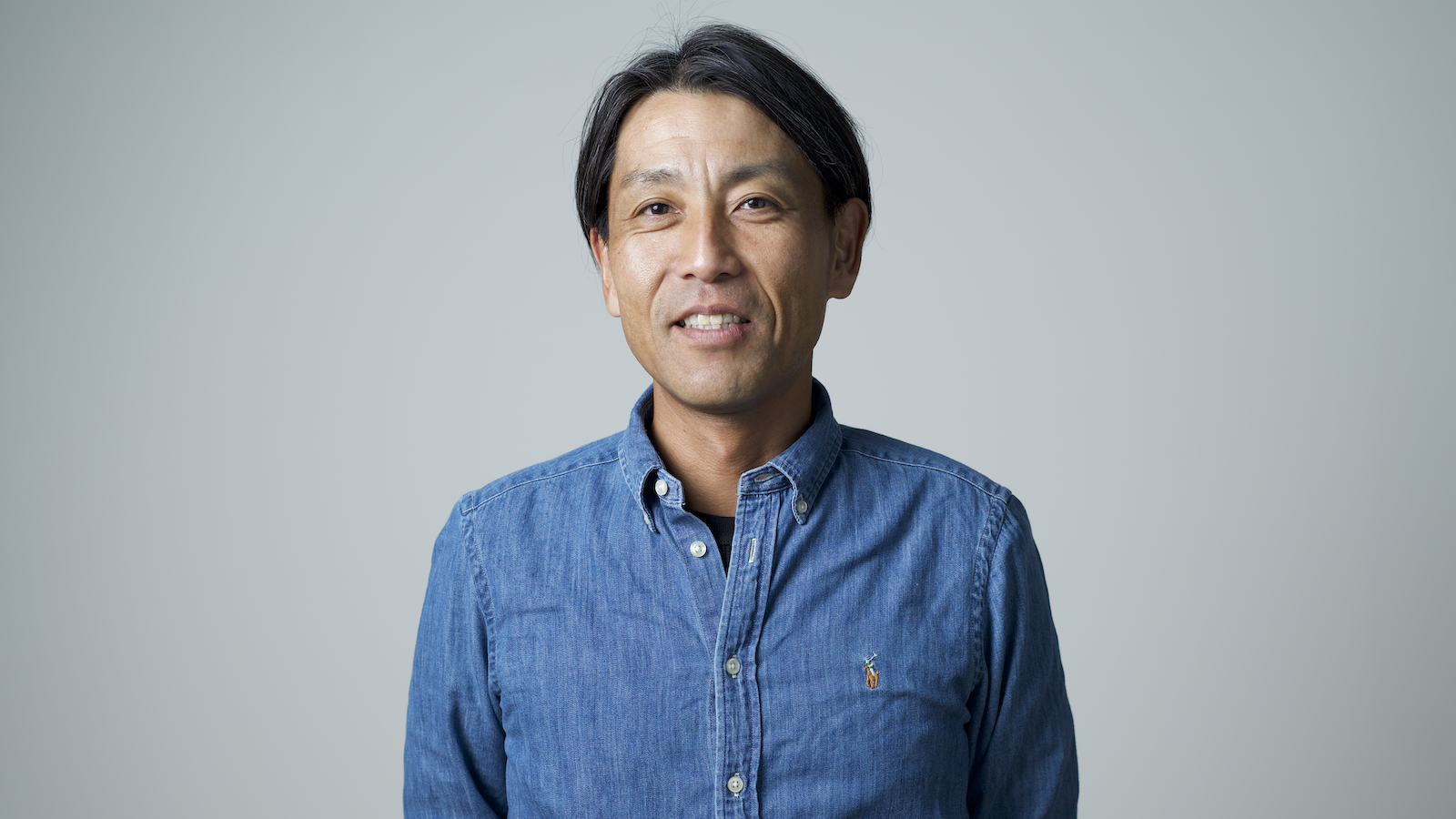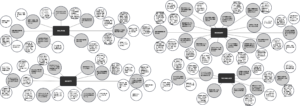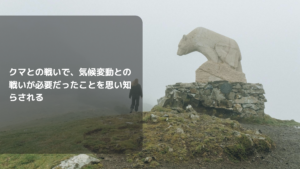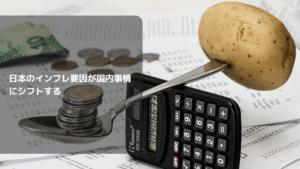この記事は、トレンドの原動力を探るマーケティングセミナー「よげんの書」で発表した「よげん」をトピックごとに解説した記事です。よげんの書のウェブサイトから無料セミナーのお申込みや、講演資料やアーカイブ動画をご覧いただけますので、ご関心ありましたらお申込みください。
2025年の夏に見られる気候変動の影響は、暑さの問題だけではなく経済や生活に深刻な変化をもたらしています。
記録的な猛暑と高い湿度
2025年7月の日本国内の平均気温は、1898年の統計開始以降で最も高くなりました(平年より2.89度高い)。特に、日本の主要都市(東京、名古屋、福岡など)では湿度が上昇し、熱帯級の蒸し暑さとなっています。これは、日本近海の海面水温が世界の平均の2倍の速さで高まり、水蒸気が大量に流入しているためです。高温と多湿により汗が蒸発しにくく、熱中症のリスクが世界でも高い水準にあると指摘されています。
猛暑による経済損失とインフラの課題
地球規模で見ると、酷暑は広範囲に影響を与え、600兆円に及ぶ経済損失の危機が迫っています。農作物の作柄悪化が進むと、2035年までに食料インフレが年最大3ポイント進む見込みです。また、カリフォルニアの山火事のように、インフラ損壊が広がるリスクがあり、その経済損失は最大40兆円に達すると推計されています。 日本のインフラは、鉄道や送電網が酷暑や豪雨に直撃されるリスクがある中で、堅牢性が世界168カ国中138位にとどまっており、対策の必要性が高まっています。
日本の食卓を襲う「猛暑インフレ」
猛暑は日本の家計と食卓を直撃し、「猛暑インフレ」を引き起こしています。
米不足の懸念: 7月は観測史上最も暑く降水量も少なかったため、新潟などで水田が干上がる状況が発生し、2025年産米の減収懸念が強まっています。
野菜・肉・魚の高騰: 暑さと干ばつの直撃により、トマトが1割、かぼちゃが2割、ピーマンが3割値上がりしています。食肉の豚肉も、暑さによる食欲不振で受胎率が低下し、高騰しています。養殖のブリは水温上昇で成長が遅れ、5割も高騰しました。
- こうした食品供給の停滞と値上がりは、家計を圧迫し、体感物価の上昇を通じて消費を下押しする懸念があります。
変化への適応と新しい機会
猛暑やコメ不足といった課題に対し、新たなチャレンジも始まっています。温暖化を背景に、田植えをせずに株を残して稲を再生させる「再生二期作」が注目され、2025年には取り組みが前年比約2倍に拡大しています。これは、特に温暖な地域(沖縄や関東以西)で、早めに1回目の収穫を行い、11月に2回目の収穫をすることで増産を狙う方法です。これは、人手不足の農家にとって、効率化を図る上でも重要です。
また、消費行動にも変化が生まれています。
屋内消費の活況: 屋外での消費(バーベキュー売上5割減、ビアガーデンの伸び悩み)が冷え込む一方で、屋内消費が活発化しています。食品の配達(Woltのアイス配達が40%増)や、大量保存志向による冷蔵庫の需要(ニトリ新機種が前年機種比3.8倍)が伸びています。映画館なども避暑需要を取り込み、来場者が増加しています (+51%)。
屋外空調の進展: 屋外での暑さ対策として、屋外空調の設置が進んでいます。ダイキンは渋谷に柱型エアコン「アウタータワー」を設置し、冷風を提供するだけでなく、人流解析や売上データ取得を通じて費用対効果を検証しています。屋外冷房が当たり前の時代が来るかもしれません。
遠い未来の危機
このまま温暖化が進むと、北極海の海氷が2030年に消滅する可能性が指摘されています。海氷の減少は太陽光の吸収を増やし、温暖化をさらに加速させるだけでなく、水循環が強まり豪雨や干ばつのリスクを高めます。