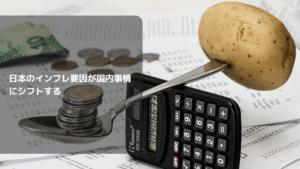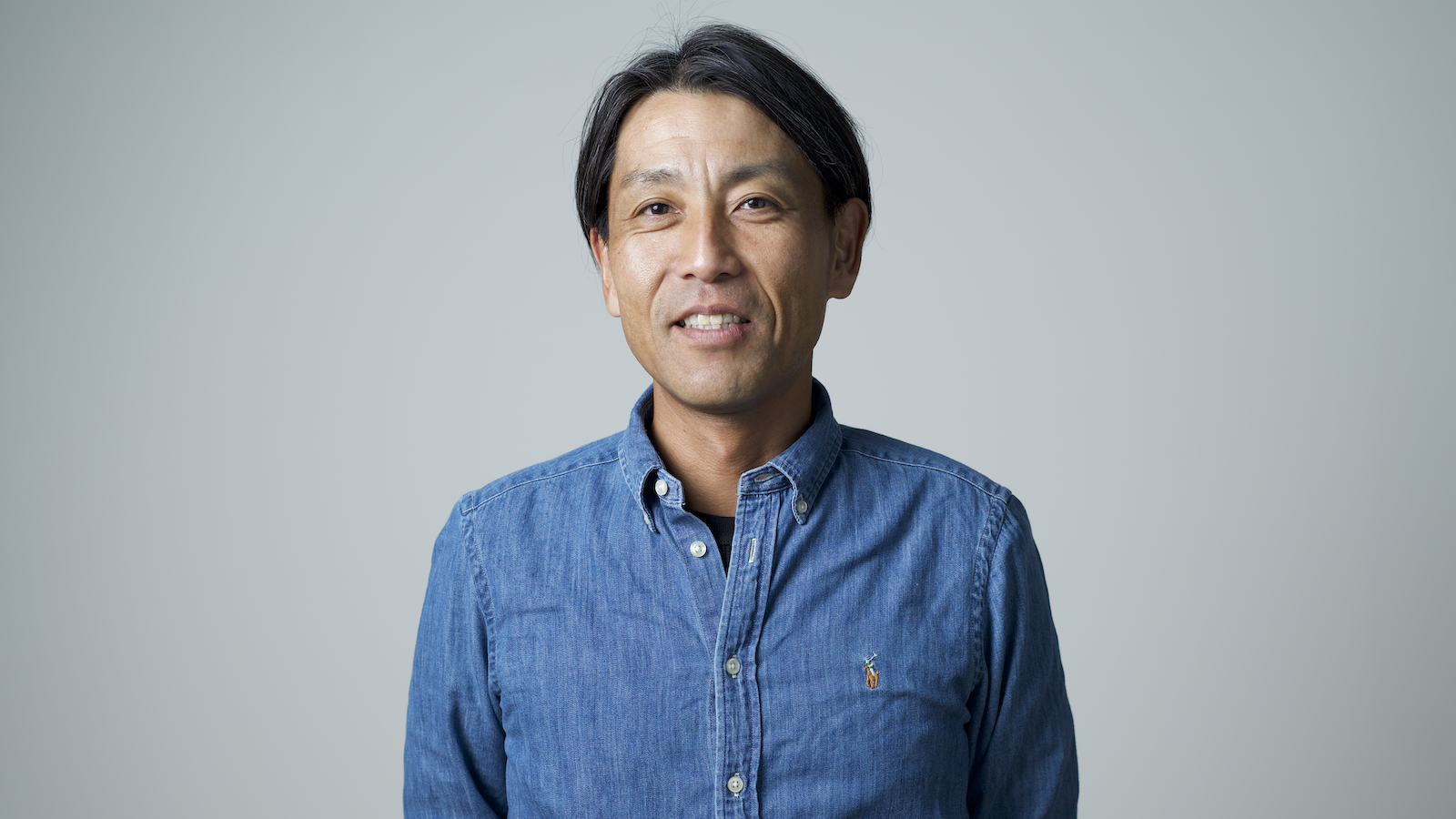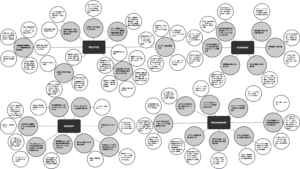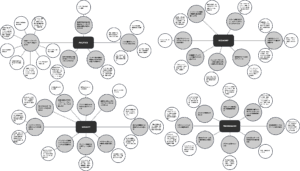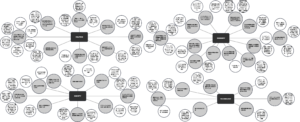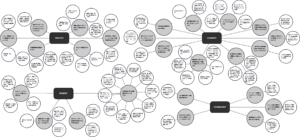この記事は、トレンドの原動力を探るマーケティングセミナー「よげんの書」で発表した「よげん」をトピックごとに解説した記事です。よげんの書のウェブサイトから無料セミナーのお申込みや、講演資料やアーカイブ動画をご覧いただけますので、ご関心ありましたらお申込みください。
外部要因から国内要因へシフトするインフレの重心
日本のインフレは続いていますが、その要因の重心が外部から国内へとシフトしています。インフレが始まった当初は、資源高や円安といった外部要因が主導していました。しかし、輸入物価指数や円安が落ち着き始めた今、インフレは国内要因、特に賃金の上昇と食料品価格の高騰が牽引しています。
コメ価格の高騰とサービス価格の反転
2025年5月の消費者物価指数は前年比で3.7%上昇し、特にコメの価格が2倍(101.7%高)になったことが影響し、食料品が総合物価上昇の過半を占めています。また、人手不足に伴う賃金上昇が反映され、サービス部門の消費者物価指数も反転し、物価上昇の要因となっています。
大企業で際立つ労働分配率の低下
賃金が上昇し物価に転嫁され始めているにもかかわらず、企業の労働分配率(利益のうち人件費に回る割合)は、2024年度に53.9%と、51年ぶりの低水準となりました。 特に、資本金10億円以上の大企業では分配率が36.8%に低下しており、利益増加に賃上げが追いついていない状況が鮮明です。一方で中小企業は人手不足の影響もあり、分配率は70.2%へ上昇しています。
過去最高の内部留保と分配の余地
内部留保(利益剰余金)は2024年度末に636兆円と過去最高を更新し、前年比で1割も増えました。現預金も268兆円という高い水準が続いています。 企業利益の適切な分配が、賃上げと経済の好循環につながる鍵であり、内部留保された潤沢な手元資金を、次なるイノベーションのための設備投資や賃上げに反映させていく余地がまだ多く残されていると言えます。