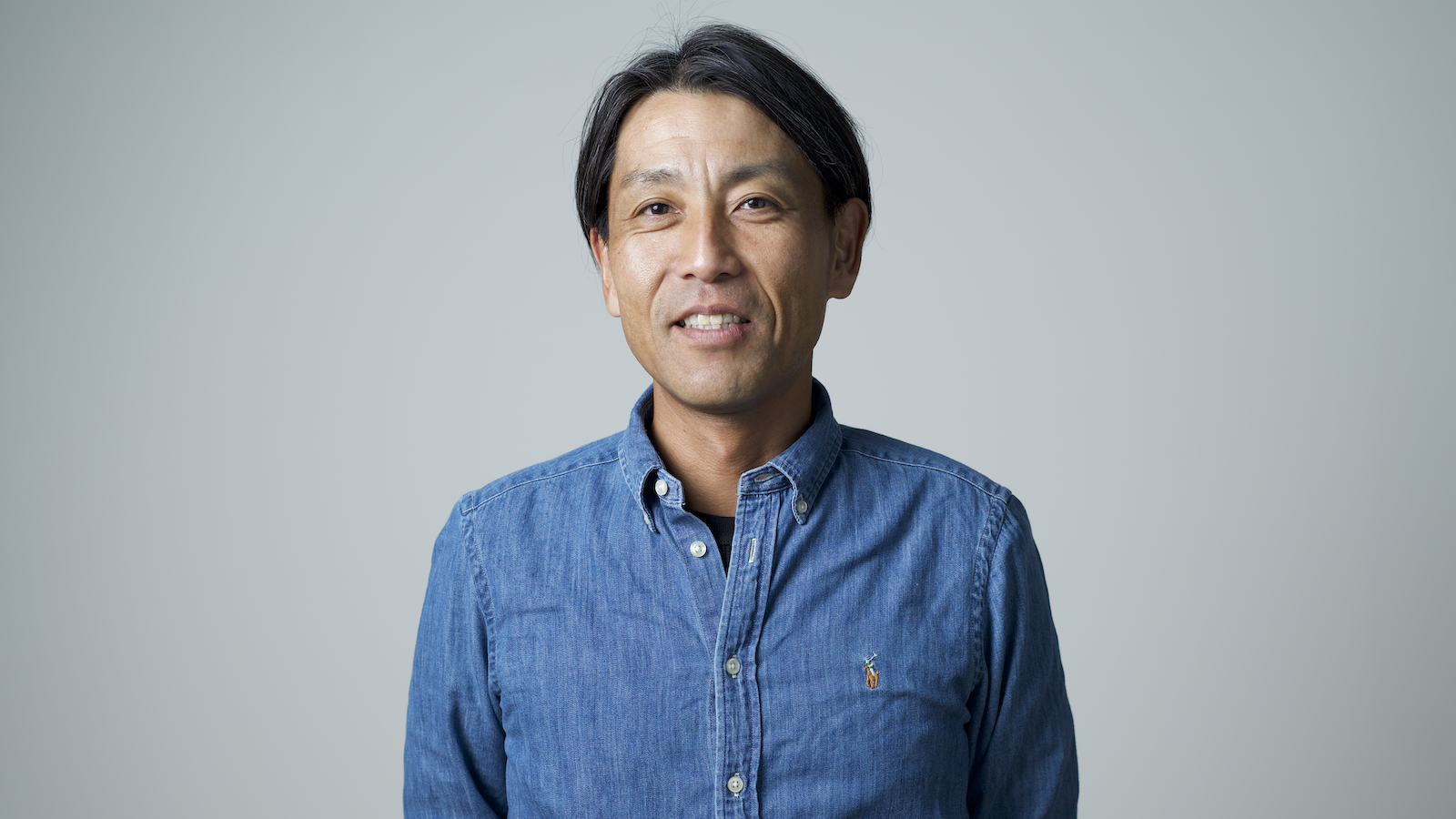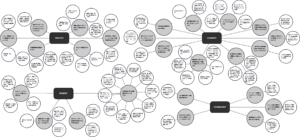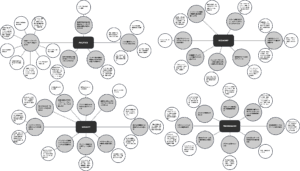この記事は、トレンドの原動力を探るマーケティングセミナー「よげんの書」で発表した「よげん」をトピックごとに解説した記事です。よげんの書のウェブサイトから無料セミナーのお申込みや、講演資料やアーカイブ動画をご覧いただけますので、ご関心ありましたらお申込みください。
北米では、かつて人気があったものの、大手メーカーの非中核となった「枯れたブランド」を再評価し、投資とマーケティングによって再生させる動きが注目されています。
ブランド再生ファンドの戦略
米国のPEファンド「ブリンウッド・パートナーズ」は、消費財(食品・飲料中心)に特化し、ブランド再生に投資しています。彼らは、大手の非中核ブランドをM&Aで切り出し、独立運営と再投資によって機動的に成長を取り戻す戦略を取っています。 例として、飲料ブランド「SunnyD」の売上を9年間で約2倍に伸ばした実績があります。
ブランド選定の3つの視点
ブリンウッド・パートナーズが候補ブランドを選定する際の視点は、マーケティングにおいて重要です。
非中核: 大手食品メーカーで優先順位が下がっているブランド。
大衆性: 幅広い層に受け入れられるポテンシャル。
想起資産: 顧客の記憶の中にあり、懐かしさを感じさせる要素(ノスタルジー)。
彼らは、この3条件で棚卸しを行ったブランドに対し、「懐かしさ」という土台に「新体験」を組み合わせることで、再購入率を高め、さらに若い世代の新規顧客獲得を狙います。例えば、SunnyDをRTD(すぐに飲める)カクテルへ横展開し、新しい飲用機会を広げています。
レコノミーとの関連性
この「枯れたブランド」の再生は、循環型経済を示す「レコノミー」の視点とも関連しています。レコノミーはリユースやリサイクルを指しますが、「レトロ」なブランドを再利用・再評価することも、一種の経済循環と捉えられます。自社内の休眠ブランドや、他社のブランド選定の視点として、「大衆性×想起資産」を持つブランドを再検討することは、新しいアイデア発想につながる可能性があります。