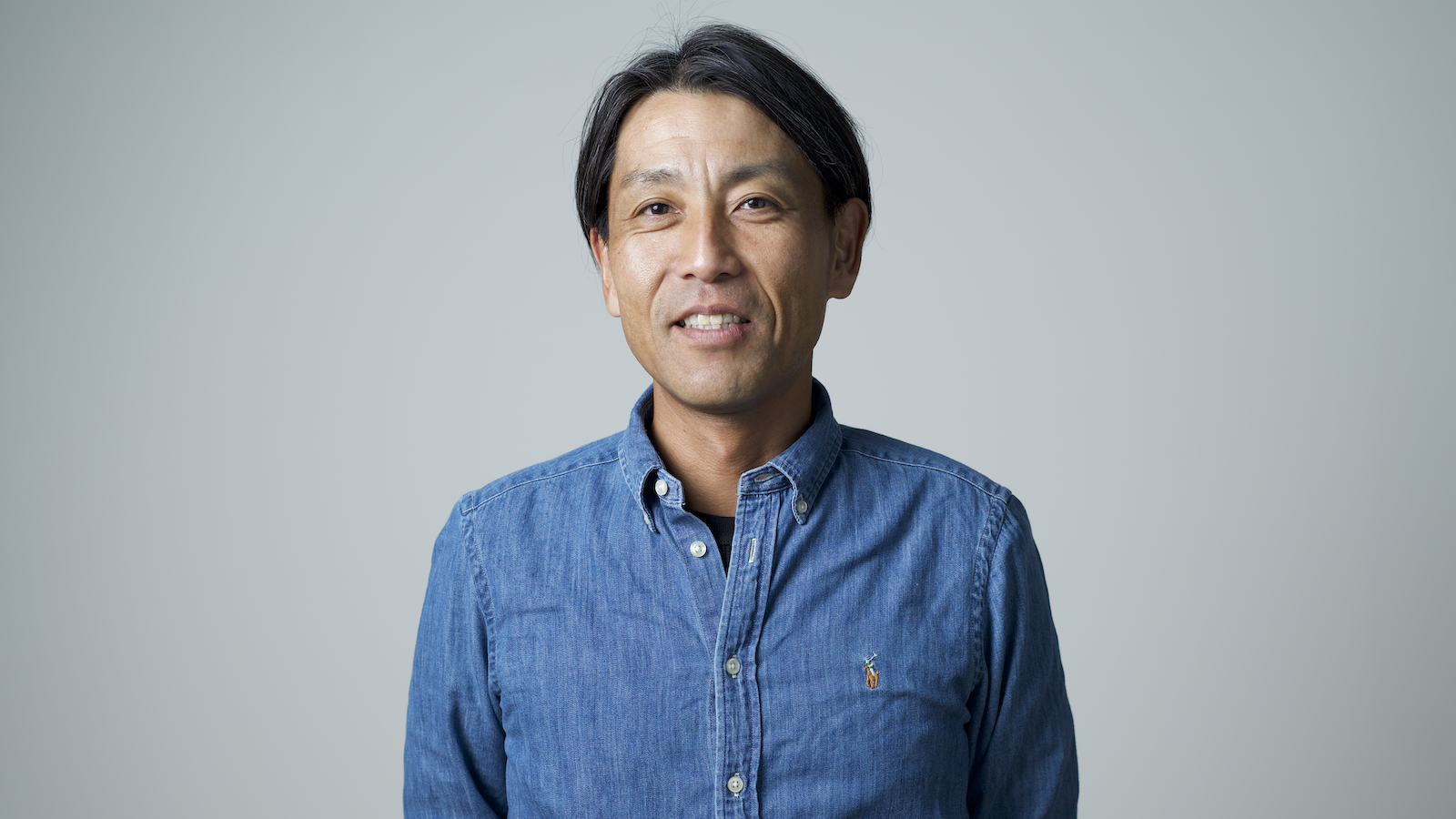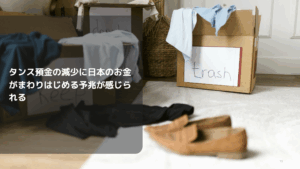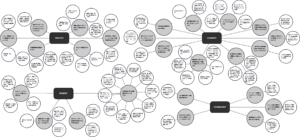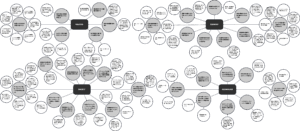この記事は、トレンドの原動力を探るマーケティングセミナー「よげんの書」で発表した「よげん」をトピックごとに解説した記事です。よげんの書のウェブサイトから無料セミナーのお申込みや、講演資料やアーカイブ動画をご覧いただけますので、ご関心ありましたらお申込みください。
若者を中心とした消費価値観が、ポイント還元率を重視する「ポイ活」から、推しへの貢献や体験を重視する「推し活」へとシフトしています。この熱量を活用した新しい金融サービスや観光商品が市場を拡大しています。
ポイント還元率より推し体験を重視するクレジットカードの台頭
国内のクレジットカード発行枚数が3億枚を超える競争の激しい市場において、「ポイ活」よりも「推し体験」を重視する若者が増えています。ポイント付与ではなく、利用額に連動して推しキャラクターの画像や動画の特典が解放されたり、収益の一部が応援先に分配されたりするクレジットカード「Nudge(ナッジ)」の利用が増加しています。提携するアイドルやスポーツチームなどの「推しカード」の種類は170を超え、2025年上期の利用額は前年同期比で2倍に伸びています。Nudgeは、高い現金払い率を持つ10代にも目をつけ、コンビニ入金や即時明細で学生でも使いやすい設計としています。
インフレ下でも強い「推し活」市場と地域経済への波及
「推し活」の市場規模は1,300万人と言われています。20代以下の64%や30代の44%が複数の推しを持ち、年間支出額は30代以下で約20万円と、高い熱量が特徴です。この熱量はインフレ下でも強い耐久性を示しており、65%の人が推し費用を減らさないと回答しています。日銀のさくらリポートでも、推し消費が移動、飲食、宿泊に波及し、地域経済を押し上げる可能性が指摘されています。JR東海も2021年から「推し旅」を開始し、宝塚の観劇ツアーなどを展開、2024年度には企画を倍増(約100企画)するなど、市場の拡大を後押ししています。
コアファン頼みによる新規参入の壁と持続可能性
一方で、「推し活」に関連するコンテンツ支出者の数は減少しているというデータもあります。これは、熱心なコア層による一人あたりの支出が最高を更新し、全体の額を押し上げている構造が見られるためです。チケットやグッズ、遠征費の値上がりが続くなか、主催者側も、関連グッズの継続的な販売やダブルキャストの導入などで、コア層の単価を高める戦略を強めています。しかし、有料配信や価格上昇により、お金を出せるコアなファンが支える構造は、新規参入の壁となっている可能性が指摘されています。ブランドやサービスは、一時的な熱狂に頼るのではなく、「好きでい続けてもらえるような」無理なく続けられる環境づくりが大切だという示唆が得られます。