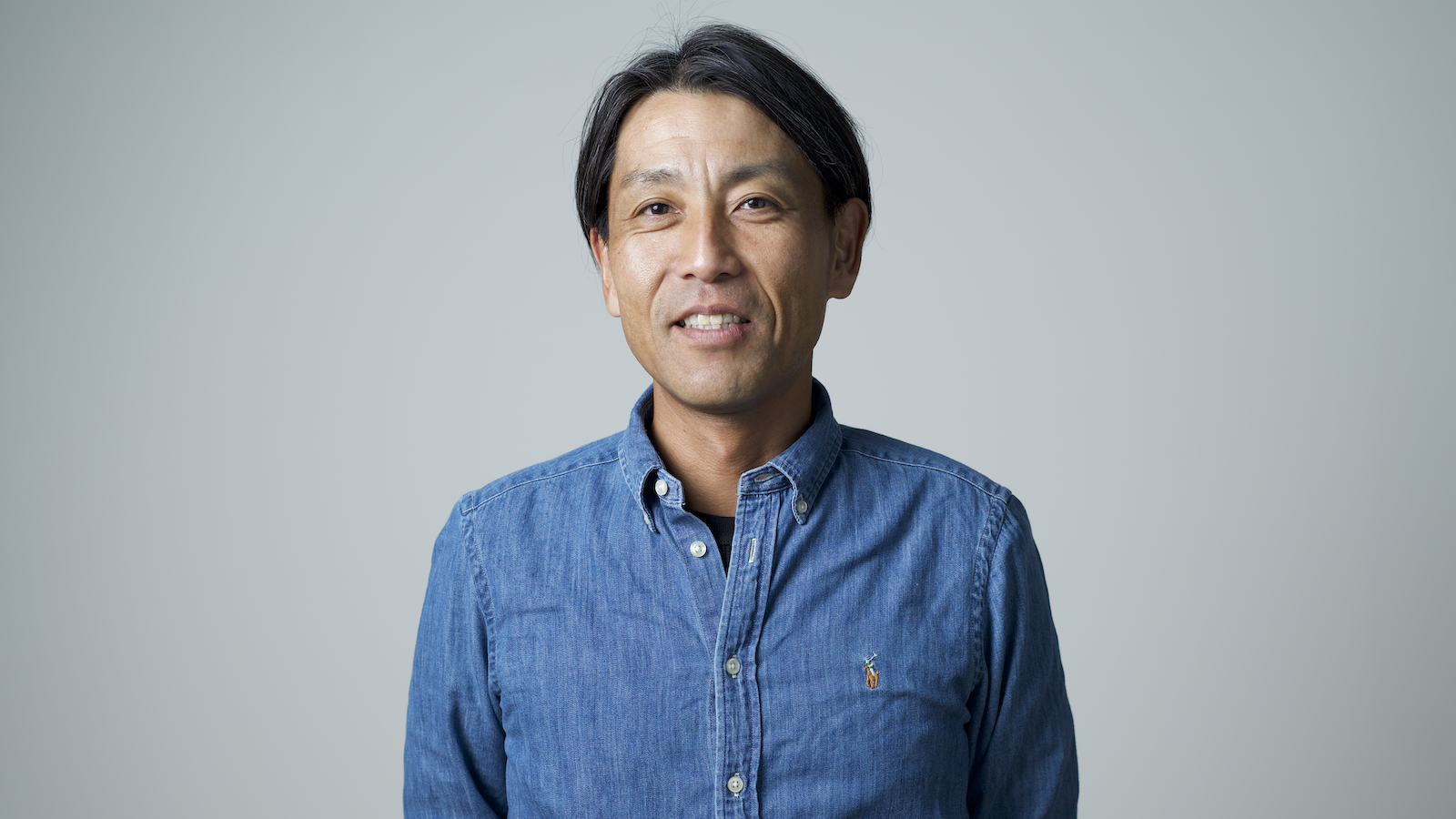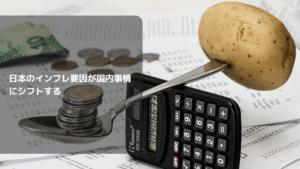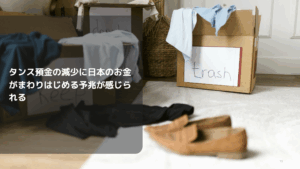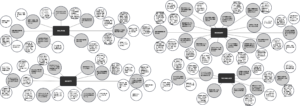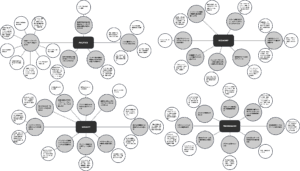この記事は、トレンドの原動力を探るマーケティングセミナー「よげんの書」で発表した「よげん」をトピックごとに解説した記事です。よげんの書のウェブサイトから無料セミナーのお申込みや、講演資料やアーカイブ動画をご覧いただけますので、ご関心ありましたらお申込みください。
共働きで高年収の「パワーカップル」世帯は増えていますが、可処分所得の増加分の大半が貯蓄に回り、実質的な個人消費は停滞しています。インフレによる実質賃金のマイナスが続く中、家計が将来への備えを重視する姿勢が明らかになっています
高額消費を牽引するパワーカップル世帯の増加
夫婦ともに年収が多い共働き夫婦、いわゆる「パワーカップル」(それぞれ年収700万円以上など)は増加傾向にあり、夫婦ともに年収1,000万円超の世帯は約11万世帯へと倍増しています。専業主婦世帯は2024年に508万世帯に減少し、若年層ほど共働き志向が強まっており、今後もパワーカップルは増えていくと想定されています。これらの世帯は、家事代行や総菜宅配といった外注支出や、不動産、教育、家電などの高額消費を押し上げています。
可処分所得の増加分が貯蓄に回る消費の停滞
勤労者世帯の可処分所得は過去10年間で約10万円増え、2024年には月52万2,569円に達していますが、消費支出は月32万円にとどまり、10年前から1万円ほどしか伸びていません。これは、増加した可処分所得の大半が貯蓄に回っていることを意味します。インフレや将来に備える志向が強まっているため、実質個人消費はコロナ前の水準に戻らず、停滞が続いています。
消費を牽引する層を増やすためには、転勤制度の廃止や硬直的な労働市場を改め、働き方を豊かにし、子育てをしながらでもパワーカップルでいられる安心感を高めることが求められます。パワーカップルの一般的な基準とされる一人700万円という年収も、今や米国やドイツなどの平均水準に届いていません。
実質賃金マイナス回復には5年かかる見込み
賃金上昇はインフレに追いついていません。2022年以降のインフレにより、実質賃金は2022〜2024年度の3年間で累計マイナス4.4%となっています。5%を超える賃上げが実現しても、インフレが続くため、家計の体感的なダメージはなかなか回復しにくい状況です。政府目標である実質賃金プラス1%/年が続いたとしても、目減りした給料を2021年度水準に戻すには約5年かかる見込みです。賃上げの定着、生産性向上、適正な価格転嫁を同時に回し、実質ベースで賃金が伸びるというノルムを途切れさせず続けることが、消費を促す好循環に必要とされます。