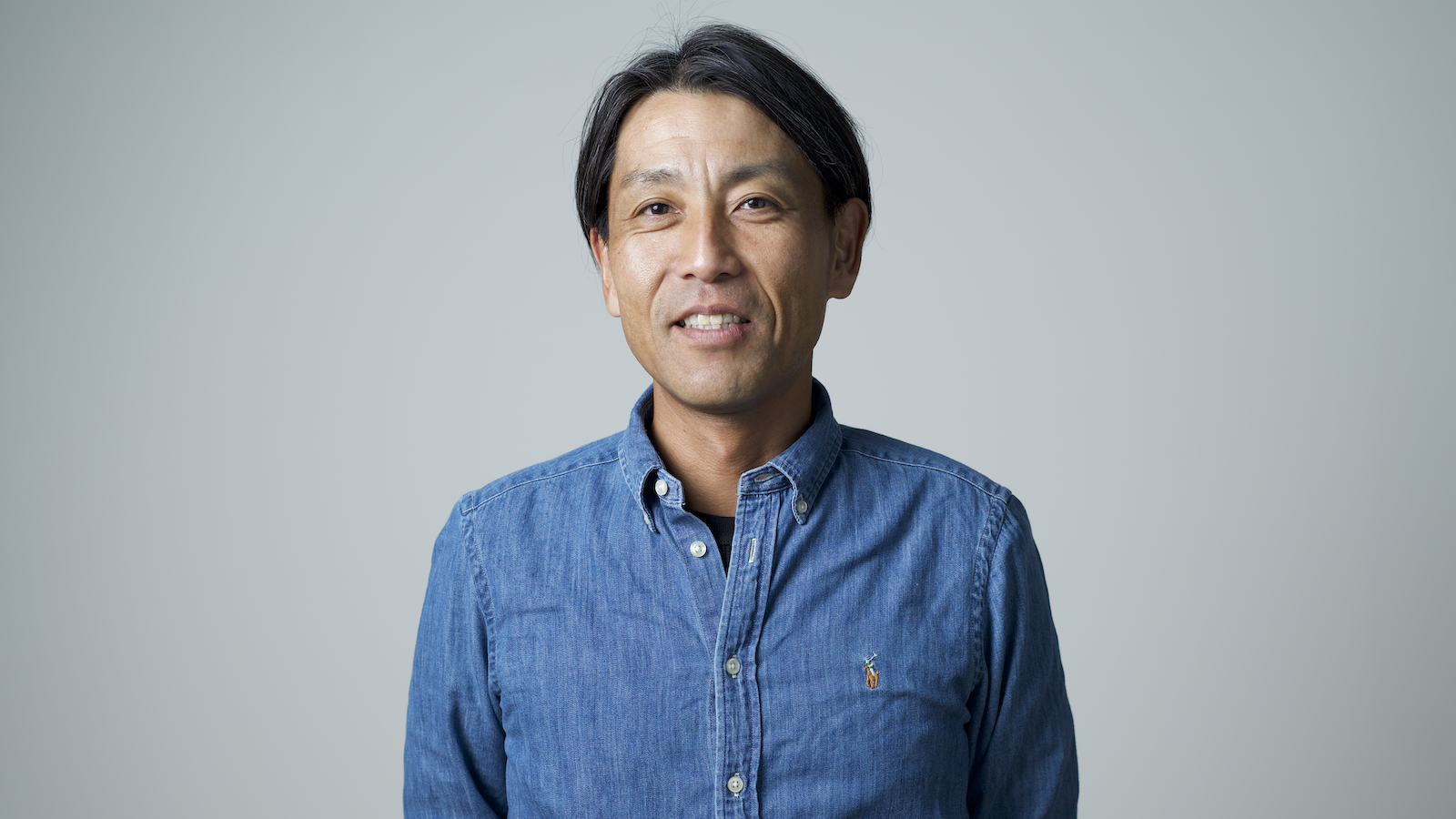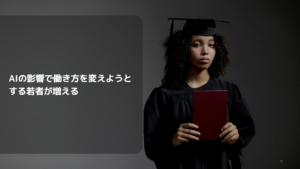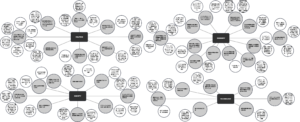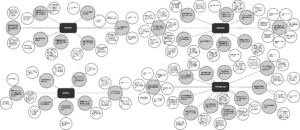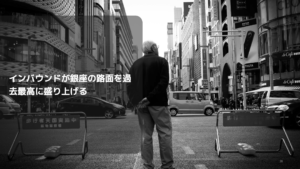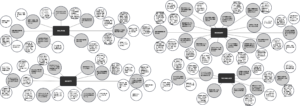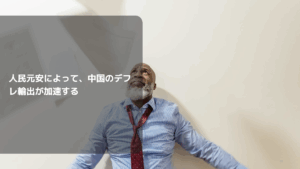本ブログは、トレンドの原動力を探るマーケティングセミナー「よげんの書」が月次でまとめているPEST分析を解説した記事です。よげんの書ではウェブサイトから無料セミナーのお申込みや、講演資料やアーカイブ動画のダウンロードが可能となっていますので、ご関心ありましたらお申込みください。
2025年10月のクリップをまとめていると、「境界線が書き換えられている」という感覚を覚えました。国と自治体の役割、仕事と家庭の線引き、国内と海外の人の動き、そして人間とAIの距離感も。どこまでを誰が担うのかという線が、少しずつ引き直されているように見えます。
今月のPEST分析では、こうした変化を Politics / Economy / Society / Technology の4つの視点から整理してみます。
POLITICS:政治
政治の「境界線」をどう描き直すのか
まず政治の領域では、「お金」と「権力」の境界線が問われました。
ふるさと納税では、一部の自治体が使いきれないほどの寄付を集めている実態が報じられました。返礼品競争の結果、全国から集めた住民税が積み重なり、地域の課題解決につながっていないケースが出ています。国が決めた制度を自治体が全力で活用した結果、国と自治体、お礼と税収のバランスが崩れつつあるという構図です。「誰のための政策なのか」という原点に立ち返る必要が高まっています。
同じように、大きな境界線の書き換えが始まったのが、自公連立の解消です。約26年続いた連立与党体制に終止符が打たれ、「安定政権」が前提だった政治は、再び流動化のフェーズに入ろうとしています。選挙制度と党のあり方を含めて、「99年体制」以降の日本政治の骨格そのものを再設計が進んでいます。
家計に近いテーマとしては、「年収の壁」をめぐる議論が続いています。専業主婦のうち約100万人が就業を希望しているとされる一方、「もっと働きたい」と実際に行動している人は決して多くありません。税・社会保険・扶養控除・家庭の事情といった複数の要因が絡み合い、「働きたいけれど、仕組みが背中を押してくれない」状態が可視化されています。ここでも、制度と現実の境界線が古いままになっているのではないでしょうか。
海外に目を向けると、トランプ政権下での就労ビザ規制の影響が早くも表面化しています。ITや会計など高度専門職の業務が国外に分散し、アメリカ国内の雇用市場には十分な恩恵が落ちていません。「アメリカで働く」という境界線が厚くなるほど、仕事そのものが国境を越えて移動するという逆説的な状況です。
長期的な視点では、宗教を信仰する人と無宗教のバランスにも変化が予測されています。人口動態のシミュレーションでは、今後数十年で「宗教を持つ人」が増え、無宗教者の比率が減少する可能性が示されています。意外なシミュレーションですが、不確実性が高まる世界で帰属先を求める動きが強まるという見立てです。
そして、トランプ大統領が近代国家の骨格をなす「4つの境界」を崩そうとしているという指摘も出ました。国家と個人、行政と司法、事実とフェイクニュース、現実の政策とSNS上のポピュリズム。こうした境界があいまいになるほど、政治に求められる説明責任は重くなります。境界を壊す力と、それを再構成する力の両方が必要なフェーズに入っています。
ECONOMY:経済
リスキリングと再エネが「次の土台」を決める
経済では、「どこからが投資で、どこまでが消費か」という線引きが問われています。
まず、重要な分岐点を迎えているのがリスキリングです。学び直しに対して休暇や給付金を制度化する動きが出てきましたが、実際に普及するかどうかは企業側の制度設計にかかっています。企業が「人材への投資」として本気で取り組むか、それとも一部の意欲的な個人だけのものとして留まるか。ここが日本経済にとっての分水嶺になりつつあります。
マクロの数字では、日本のGDPがインドに抜かれ世界5位に転落するとの予測が示されました。この順位そのものに一喜一憂する必要はありませんが、「人口が増え、生産性も伸びる国」と「人口が減り、労働時間も減る国」の差がいよいよ数字に現れたと言えます。
エネルギー面では、世界全体で再生可能エネルギーが石炭を上回り、最大の電力源になりました。価格面でも豪州炭などは大きく値を下げ、再エネへの長期転換が既定路線であることがはっきりしてきました。同時に、野菜のタネの自給率が1割しかないというニュースもあり、気候変動や円安によるコスト増が食料安全保障の新たな課題になっています。エネルギーと食料という2つの基盤をどう国内で確保するかが、中長期のテーマになります。
企業サイドでは、「賃上げ」だけではなく「株式報酬」で社員を資本家にしていく動きが広がっています。従業員が自社の株価を通じてリターンを得る仕組みは、給与原資を抑えつつインセンティブを提供する手段として注目されています。ただし、株価は景気や市場の影響も大きいため、短期的な変動に左右されない設計が求められます。
消費のフロントでは、家電量販店でEVを販売するような「売り場の境界線の書き換え」が進んでいます。イオンがBYDと提携し、店舗の一角にEVコーナーを設置する構図は、モビリティと小売の境界を曖昧にします。福利厚生としてマッチングアプリを提供する銀行など、「企業がどこまで社員の生活に入り込むか」という線引きも変わりつつあります。
観光では、インバウンドが増える一方で、日本人観光客が減っている現実も見えてきました。海外からの旅行者で宿泊施設が混雑し、料金が高騰した地域では、日本人が旅行を控える傾向が出ています。観光地の「稼ぎ」と「暮らし」のバランスをどう取るかが、これからの地域戦略の課題になります。
また、跡取り不足に悩む中小企業の世界では、「跡取り娘」を地域全体で支援するプロジェクトも始まっています。名字変更が承継の壁になるといった日本独特の問題も浮き彫りになり、家業の継ぎ方そのものをアップデートする必要が出てきました。
最後に、街のブランディング手法として「香り」を使う試みがはじまっています。さいたま市が市民投票で「街の香り」を選び、グッズやPRに活用しようとしている例は、五感を使ったブランドづくりの象徴です。視覚・聴覚中心だったブランディングが、嗅覚という新しい境界をまたぎ始めています。
SOCIETY:社会
家族と仕事と季節の境界が変わる
社会の領域では、生活の前提が静かに変わりつつあります。
家電市場では、単身・夫婦のみといった少人数世帯向けの高機能家電が注目を集めています。「スペックは高いがサイズはコンパクト」という製品が増え、世帯構成の変化が家電の前提を変えています。家族が前提だった暮らしのインフラが、「一人か二人」を起点に設計されるようになっています。
人口構造では、日本で生まれる新生児のうち約3%が外国人であるという数字が出ました。絶対数としてはまだ少ないものの、低出生数を補う存在になりつつあり、共生をどう設計するかが課題になっています。
消費行動の面では、Z世代の「EIEEBモデル」が実際のビジネスに反映され始めています。歯ブラシや洗顔といった日用品を、「指先でちょっと試すだけで楽しいプロダクト」として再設計する動きは、Enjoy(楽しさ)→Interest(興味)→Experience(体験)→Engagement(関与)→Belong(帰属)という流れを意識したものです。機能だけではなく、感情のグラデーションをどう作るかが商品開発のポイントになっています。
医療では、オンライン診療が地方を中心にしっかり伸びています。小児科の365日オンライン相談など、特定のニーズに特化したサービスが浸透し、医療アクセスの地理的な境界を薄めています。世代別の体力データでは、シニア層の体力が向上している一方、30代の低迷が目立ちます。高齢者は健康意識と時間の余裕から運動習慣を持ちやすく、むしろ中堅世代のほうが運動不足に陥りやすい構造が見えてきました。
働き方に目を向けると、「マッチョ」な企業文化を変えようとする動きが加速しています。体力勝負・長時間労働が前提だった業界では人材が集まりにくくなり、飲食店や工場を中心に担い手不足が深刻です。女性の採用やバイアス研修など、組織の価値観そのものを変えなければ持続できない産業が増えています。
働き方を考える必要に迫られる人も増加傾向です。不登校の増加が親の離職リスクを高め、「ビジネスケアラー」と呼ばれる立場の人を増やしています。企業が休職制度や時短勤務でケアを支える動きを強めているものの、仕事とケアの両立はまだ簡単ではありません。ケアの負担を家庭の中だけに閉じ込めない仕組みづくりが急務になっています。
気候変動の影響も、生活レベルで実感されるようになっています。データによると、日本の夏はこの40年で約3週間長くなり、春と秋が短くなっています。エアコンや衣類、レジャー、勤務環境の設計まで、「長い夏」を前提にした社会設計が必要になっています。
海外では、少子化先進国とされる韓国で、若者の変化に関するデータの開示が進んでいます。高学歴ニートが若者の5%を占める現実や、「非婚の母」が増えている状況を政府が公表し、個別支援を進めています。伝統的な家族観よりも、個人の生き方をどう支えるかという視点が前面に出ています。
そして、AIの影響も若者の働き方を揺さぶっています。米国では、学位があってもホワイトカラーの就職が難しくなり、一部の若者が高収入を期待してブルーカラー職を選ぶ現象が報じられました。しかし実際には「ブルーカラー富豪」が簡単に生まれるわけではなく、AIと自動化の波の中で若者の失業率はむしろ上昇しています。ここでも期待と現実のギャップが見えてきます。
TECHNOLOGY:技術
AIが“第2の社会”として立ち上がる
テクノロジーの領域では、AIが「もう一つの社会」として動きはじめています。
研究分野では、AIが10年がかりの研究プロジェクトに匹敵する成果をわずか2日で出してしまう事例が報じられました。AIが「計算機」から「科学者」へと役割を変えつつあります。これにより、研究者の仕事は「解く」ことから「問いを設計すること」へと境界を移していく可能性があります。
サイバー攻撃との攻防も、DXの進展とともに激しさを増しています。システム統合が進んだ企業ほど、1つの攻撃で広範囲に被害が広がりやすく、守りの設計を最初から組み込む「セキュリティ・バイ・デザイン」が必須になっています。
一方で、AIを悪用しようとする動きに対抗する新しいアイデアも生まれています。詐欺電話やフィッシングに対して、AIおばあちゃんが詐欺師を逆に翻弄するという取り組みは、攻撃側と防御側の双方がAIを使う「代理戦争」の時代に入ったことを象徴しています。
私たちとAIの距離感についても議論が活発です。AIと恋愛関係のようなコミュニケーションを取ることをどう捉えるのか。「理想はドラえもんのような距離感だ」という意見もあり、友人でも恋人でもない「相棒としてのAI」をどこまで受け入れるかが問われています。
ハードウェアの世界では、米中を中心にAIロボットの競争が過熱しています。全天候型のヒト型ロボットが実用化されるなど、ロボットは工場内だけでなく屋外の現場にも出ていく段階に入りました。ソフトバンクGがスイスのロボット企業を買収したニュースも、その競争の激しさを物語っています。
暮らしの中でも「AIエージェント」が静かに浸透し始めています。心拍を計測し生活アドバイスをしてくれるミラーや、家庭の節電を提案する家電など、私たちの日常を観測し、行動をそっと修正してくれる相棒としてのAIが増えています。モビリティでは、自動運転バスが地方都市や万博会場で実証段階から実用段階へと移行しつつあります。運転手不足を補う手段として評価される一方で、事故時の責任の所在など、新たなルールづくりも求められます。
エンターテインメントでは、感情AIを使ってゲームの没入感を高める技術が進んでいます。心拍や発汗などの生体データを取り込み、プレイヤーの状態に合わせて演出を変える試みは、「ゲームの中の感情」と「現実の感情」の境界をさらに曖昧にします。同時に、依存リスクへの対策をどうするかという課題も浮上しています。
境界を壊すだけでなく、「どこに線を引き直すか」を考える時期です
2025年10月のニュースをPESTで眺めると、共通しているのは「境界が書き換わりはじめている」ということでした。
- 国と自治体、連立与党と野党、宗教と無宗教
- 仕事と家庭、賃金と株式報酬、観光と生活
- 家族のかたち、日本人と外国人、オンラインとオフライン
- 人間とAI、現実世界とデジタル世界
これまで当たり前だと思っていた線引きが、少しずつ動いています。重要なのは、ただ境界を壊すことではなく、「どこに新しい線を引き直すのか」「その線を誰が決めるのか」を、私たち自身が意識的に選ぶことだと感じます。
AIも再エネもリスキリングも、「次の境界線をどう描くか」という話の一部です。
2025年10月は、そのことをあらためて示唆してくれる月になりました。